「お母さんがお家でこっそりする!我が子の発達チェック」
LINE登録限定でプレゼント(詳しくは文末LINEボタンをクリック)
【開講】発達障害オンライン講座
「3ヶ月で発達障害の特性を持つ我が子の問題行動に振り回されなくなる!
子どもの癇癪とお母さんのイライラを減らしお互いが穏やかに過ごすための
3STEP」詳しくはコチラ→★
「お母さんがお家でこっそりする!我が子の発達チェック」
LINE登録限定でプレゼント(詳しくは文末LINEボタンをクリック)
【開講】発達障害オンライン講座
「3ヶ月で発達障害の特性を持つ我が子の問題行動に振り回されなくなる!
子どもの癇癪とお母さんのイライラを減らしお互いが穏やかに過ごすための
3STEP」詳しくはコチラ→★
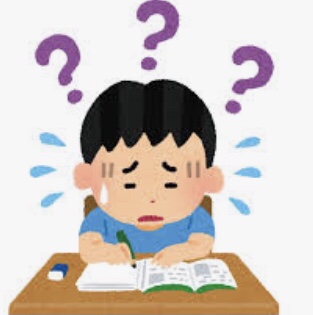
心理学・脳科学をもとに親子の困り感を解消し、発達障害の特性を強みに変えて自信を育み、親子ともに”自分らしく生きる”を実現させる
「発達障害専門カウンセラー」立川洋子です。
子どもの学校の宿題や家庭学習を見ていて、教科書やノートはちゃんと見えている様子なのに、ノートに文字を書くと枠や罫線におさまらずにはみ出してしまうことはありませんか?書くこと自体に苦手さを抱えていそうな様子はありませんか?
特に小学1年生の場合、4月のこの時期は自分の名前やひらがな50音の書き取り練習の宿題が出ることが多いと思います。ひらがなは基本ですので、これから本格的に始まる学習を頑張るためにもしっかりと覚えることが必要です。
~~~~~~~~~~~~~~~
小さなホワイトボードで力を入れずに書くことから始めてみる
~~~~~~~~~~~~~~~
100均で小さなホワイトボードが売っていますので、それを子どもとお母さん用に用意をしてみましょう。
書くことや枠内に収めて書くことに苦手さを抱えている場合、文字のバランスや書き順、筆圧や姿勢などが独特な様子が並行して見られる場合がありますが、まずは”書く”ことに負担を今以上に抱えないようにするためにホワイトボードで試し書きをすることを取り入れてみてください。
ホワイトボードの良さは、鉛筆と消しゴムで書くのとは違い、手の力を多く必要とせず、手軽に書き消しができます。何度も何度も手軽に練習ができますし書いた文字の微調整が本人自らしやすいのが特徴です。
まずはお母さん用のボードにお手本の文字を書いて見せてください。その時、子どもにはホワイトボードに目を向けさせたのを確認し、筆順を声で言ってから実際に書くと良いです。つまり、いっかくごとに「いち」と言ってから実際に一角目を書く、「に」と言ってから二角目を書くという具合です。
これは、書くことと話すことが同時だと、見ることと聴くことを同時に子どもは情報処理するようになるのでエネルギーを沢山使うことになるのを防ぐ為です。言い換えると集中力を最小限にするイメージです。
お母さんがやって見せたら次はお子さんの番です。お子さん用のボードに実際に書かせてみましょう。お母さんが「いち」と言ったら子どもが書いてみるのも良いですし、お子さんが自分で言って書くでも構いません。
書き終わったら、まずは書いた文字や書くことを頑張った子どもを褒めることも忘れずにし、実際にノートに書いてみましょう。
このようなホワイトボードと書いて見せる工夫を凝らす指導は、実は日本語教育で外国人に平仮名指導をする時に活用されているメソッドの一つで、以前日本語教師をしていた頃に現場で行う定番手法の一つでした。日本語教育だけでなく、家庭で簡単に出来る手法の一つなので是非お試しください。
ちなみに我が家の息子(発達障害 自閉症スペクトラム)もノートの枠に文字を収めて書くことが出来ませんでした。文字の読み書き、特に音読はたった1ページを読むのも30分近くかかっていました。ホワイトボードでの練習をとりいれて変化はありましたが、十分改善しないことから他の課題を模索したこともあります。それは「見え方」の課題です。この点についてはまた後日お話ししたいと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
最初の一歩は”話してみること”
◆1つでも当てはまる方は、個別相談カウンセリングをお試しください。
お申込みはコチラ→★
◆お家でこっそり我が子の問題行動を改善したい方は「発達障害オンライン講座」がお勧め
お申し込みはコチラ→★
◆LINEでのお問合せ、お申込み、簡単なご相談も可能
LINE登録の方限定のお知らせやイベントの先行案内や特別枠がありますので、是非登録してくださいね。
発達子育てを頑張るお母さんのための駆け込み相談室
発達障害専門カウンセラー 立川洋子(たつかわようこ)
E-Mail:tatsukawayoko@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/kakekomisoudan/
Instagram: https://www.instagram.com/tatsukawayouko/
発達障害オンライン講座: https://yoko-tatsukawa-s-school.teachable.com/p/3
「”書く”が苦手な場合、小さなホワイトボードで力を入れずに書くことから始めてみる」への 1 件のコメント
コメントは受け付けていません。